ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農業者・経営 > 鹿児島県立農業大学校 > 畜産学部養豚科の主な取組
更新日:2025年12月25日
ここから本文です。
畜産学部養豚科の主な取組
校内プロジェクト・意見発表会(令和7年12月)
全校学生が一堂に会し,校内プロジェクト・意見発表会が開催されました。
これは,各学科の代表がプロジェクト学習の成果や農業・農村についての意見を発表し,日頃の学習成果を競うものです。
養豚科からは,プロジェクト発表の部で1名の代表者が発表しました。
残念ながら,九州大会代表へは選出されなかったものの,自らの努力と成果をしっかりとまとめて堂々と発表することができました。

プロジェクト発表の部(2年田村優依)
「人工哺乳が哺乳子豚に与える影響」
農大祭で黒豚肉販売(令和7年12月)
鹿児島農大では,年に1回キャンパスを開放して『農大祭』を開催し,各種イベントや各学科で育てた農産物の販売を行っています。
養豚科では,1,2年が協力して農大農場で子豚から育て上げた黒豚肉を販売しました。


肥育豚における豚体重推定装置の活用(令和7年7月~12月)
肥育豚は体重110kgを目安に出荷されますが,大きくなった豚を1頭ずつ体重計で測定するには多くの労力を要します。
そこで,豚体重推定装置(デジタル目勘)を活用し,出荷体重の推定値精度と労力軽減効果について検証を行いました。
豚体重推定装置は,出荷前後の豚を画面のガイドに合わせて撮影すると推定体重が表示されます。
測定時間は25秒程度で,体重計での測定より短時間・少人数での測定が可能であること,推定精度も高いことがわかりました。
今後さらなるデータの蓄積を図り,現場でのスマート機器活用に役立てていきたいと思います。


農家留学研修&報告会(令和7年11月)
農大では,実践教育の一環として,県内各地の先進農家等において40日間の農家留学研修を行っています。
養豚科でも,2年生7名が県内3件の法人に分かれて研修を行いました。
研修終了後は,各自の研修成果を報告する報告会を開催しました。
生産現場での研修を通じ,学校では学ぶことのできない多くの経験をさせていただいたようです。
受け入れ先のみなさま,ありがとうございました。

母豚への人工授精実践
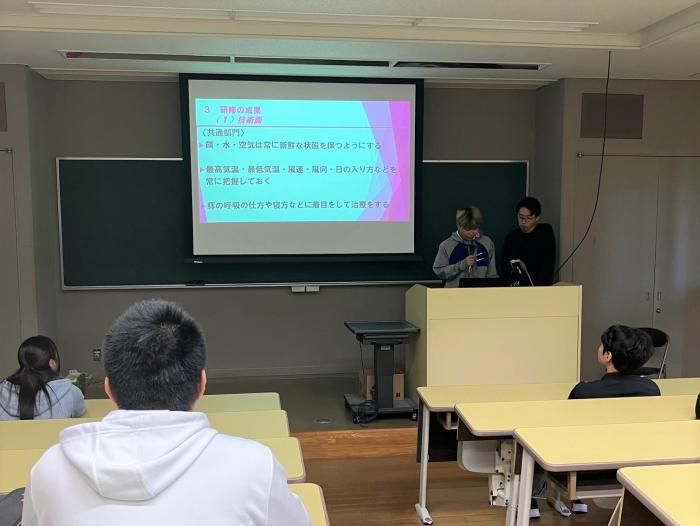
農家留学研修報告会
オープンキャンパスで学科紹介(令和7年8月)
農業大学校の雰囲気や教育内容を直接体験し理解を深めていただくため,進学希望者を対象にオープンキャンパスを開催しました。
養豚科では,家畜防疫の観点から農場での実習体験は行いませんでしたが,動画での農場紹介や黒豚クイズを行いました。
養豚科では,母豚の繁殖から子豚育成,肥育までの一貫経営を,大型種(白豚)とバークシャー種(黒豚)の両方で学ぶことが可能です。
また,少人数のアットホームな雰囲気で,非農家・非農業系高校出身の先輩方も多く活躍しています。
今後も定期的にオープンキャンパスを実施予定(次回:令和8年2月)です。
興味のある方は,是非ご参加ください。


北海道研修(令和7年7月)
海外での悪性伝染病の発生や円安による物価高騰の影響を受け,訪問先を国内(北海道)に変更し,畜産学部2年生が3泊4日の研修を行いました。
養豚科は,放牧養豚に取り組んでいる2つの農場を訪問しました。
十勝ロイヤルマンガリッツアファームは,ハンガリー原産で「食べる国宝」と呼ばれる希少なマンガリッツア豚を飼育しており,飼料は北海道産を使用し,より自然に近い飼養管理にこだわった農場でした。脂質の融点が低いという品種特性どおり,とろけるような脂身のお肉でした。

株式会社エルパソは,世界的にも珍しい24時間完全放牧で,イギリス原産のケンボロー種,国内では唯一のドイツ原産のシュヴェービッシュ・ハル種を飼育していました。どろぶたのブランド名で出荷しており,直営レストランで肉厚なステーキをがっつりいただきました。

農業機械関連講義を受講(令和7年5月)
入学間もない1年生が,農業機械士養成研修と小型機械利用の研修を受講しました。
農場での機械利用を見据えて,真剣な面持ちで取り組んでいました。

農業機械士養成研修で大型特殊(農耕用限定)免許を取得

小型機械利用研修
畜産学部1年生合同体育(令和7年4月)
畜産学部の新入生27名が,合同体育(バドミントン&バレーボール)で交流を図りました。
今年度は養豚科と酪農科の入学生が少ないため,肉用牛科の学生とも連携を密にし,畜産学部一丸となって頑張っていきましょう。

人工授精講習会(令和7年1月)
畜産学部の学生にとって,最後にして最大の難関である家畜人工授精師の免許取得にむけた「家畜人工授精講習会」が,3週間にわたり開催されました。
関係法規や家畜繁殖に関する講義だけでなく,人工授精等の実技を集中的に学びました。
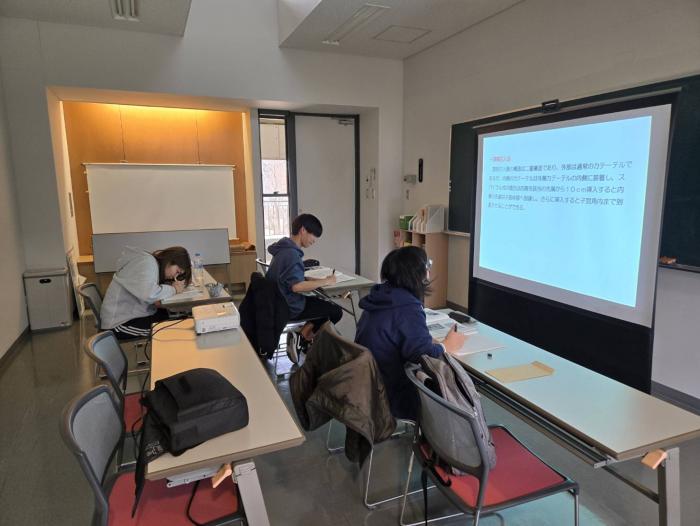
豚の人工授精に関する講義

顕微鏡での精液性状確認
畜肉加工実習(令和7年1月29日~30日)
養豚科と酪農科1年生が2日間にわたり畜肉加工実習を行いました。
豚肉をミンチにして香辛料等を加えたら,スタッファーやミンサーで豚腸・羊腸に充填します。
腸が薄く破れやすいので,詰めるのに苦労しているようでした。
整形後,大型燻製機に入れると,本格的なフランクフルトとウインナーができました。
ベーコンと焼豚も作りました。
実習を通して,衛生管理の重要性や畜肉加工の手法を学ぶことができました。

ブロック肉にピックル液を注入

焼豚の内部温度を確認
農大祭で農大産黒豚肉を販売(令和6年12月14日)
鹿児島農大では,年に1回キャンパスを開放して『農大祭』を開催し,各種イベントや各学科で育てた農産物の販売を行っています。
養豚科では,農大農場で子豚から育て上げた黒豚肉を販売しました。
自分たちが育てた豚を皆さんに直接販売する初めての機会となりました。

農大産黒豚肉の販売

県知事にパネルで学科の取組を紹介
研究プロジェクト実績発表会(令和6年9月18日)
畜畜産学部3学科合同で,研究プロジェクト実績発表会を行いました。
これは,2年生が各個人の研究プロジェクト実績をパワーポイントにまとめて発表するものです。
皆緊張した様子ながら,1年間取り組んだ成果をしっかりと発表することができました。
農業開発総合センターの農業専門指導員や畜産試験場の研究員を助言指導者に招き,多くのアドバイスをいただきました。最終的な実績まとめに活かしていきます。

実績発表会資料より
研究プロジェクトの豚肉食味試験(令和6年7月25日)
養豚科2年生が,研究プロジェクトの一環として,アニマルウェルフェア試験豚(柵なし分娩+放牧育成)と通常飼育豚(柵あり分娩+通常育成)の食味比較試験を行いました。
学校関係者に2種類の豚バラ肉をしゃぶしゃぶで食べ比べてもらい,肉のおいしさを評価してもらいました。
結果はプロジェクトまとめに活かしていく予定です。


畜産学部北海道研修(令和6年7月11日~14日)
海外での悪性伝染病の発生や円安による物価高騰の影響を受け,畜産学部では研修先を国内(北海道)に変更し,3泊4日の視察研修を行いました。
3科共通では,大規模酪農家や農業の総合コンサルタント会社,広大な観光農園などを視察研修しました。
各学科で分かれての研修では,希少種であるマンガリッツア豚の放牧農場を視察し,加工品を活用したグリーンツーリズムについても学びました。

マンガリッツア豚の放牧

マンガリッツア豚生ハムのランチプレート
子豚のワクチン接種と発育調査(令和6年4月)
養豚農場では,生産性向上と経営安定を図るため,伝染性疾病の予防管理が重要です。
農大でも適正な飼養管理と清掃消毒に加え,獣医師等の指導の下計画的なワクチン接種を行い,伝染性疾病の予
防に努めています。


(写真1)ワクチン接種
(写真2)発育調査
よくあるご質問(畜産学部養豚科)
よくあるご質問(全体共通)
関連リンク
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください